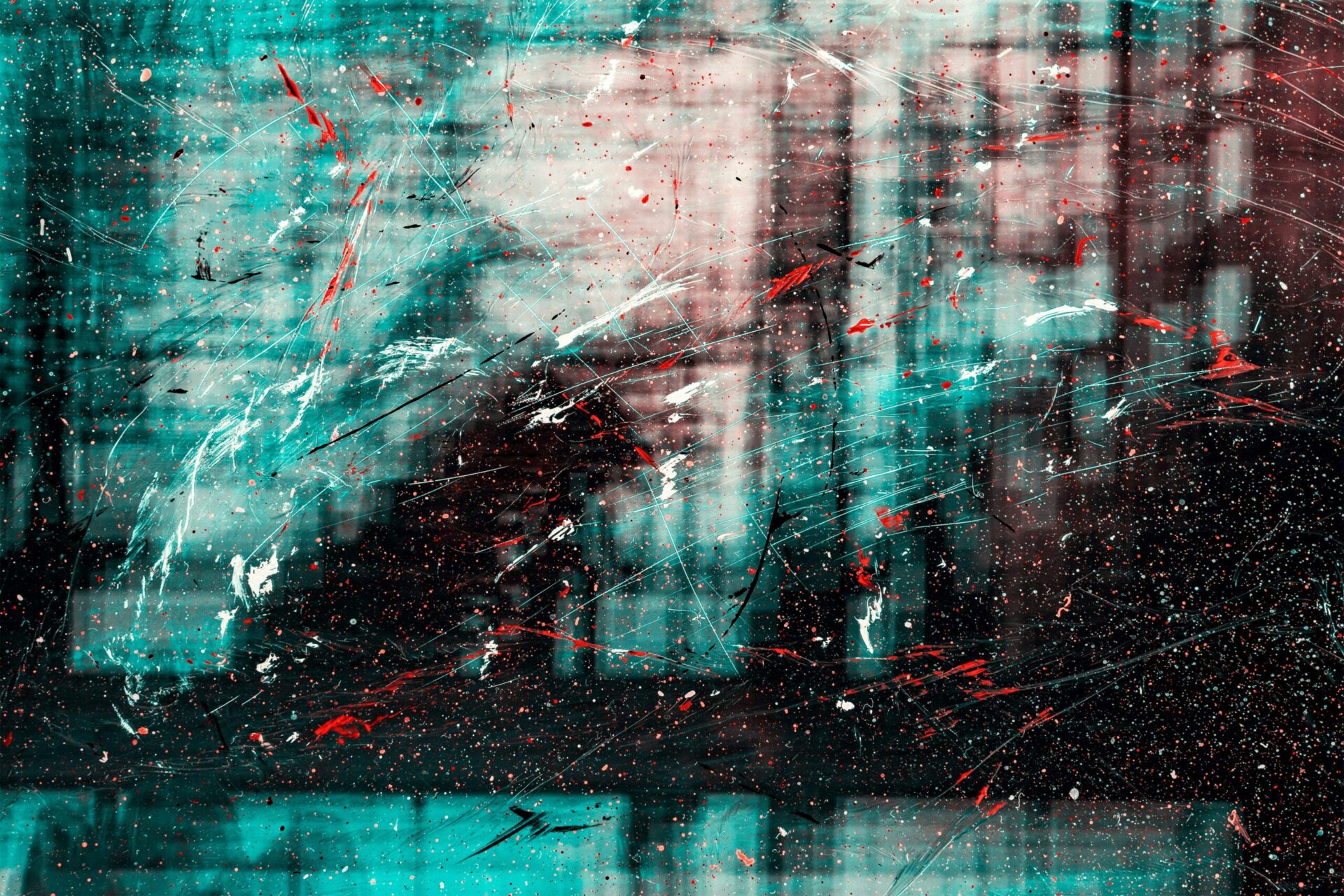空想絵画 feat. 堀込泰行

淡々としたエレポップといえばよいのか、不思議な魅力を放つ楽曲。トベタ・バジュンのアルバム『青い蝶』(2008年)に収められた「空想絵画」は何度もリピートしたくなる一曲だ。プログラミングによって構築されたエレクトリック・サウンドでありながら、しなやかな質感を持つ耳あたりが良いアレンジ。そして、これまた淡々としたヴォーカルが夢幻的な歌世界を形作っていく。
「空想絵画」でフィーチャーされたヴォーカリストは堀込泰行。この当時はキリンジのヴォーカリストとして確固たる地位を築いていた。キリンジは1996年に堀込泰行と実兄である堀込高樹で結成された2人組のグループである。1997年にインディーズでデビューし、翌1998年にシングル「双子座グラフィティ」でメジャー・デビューを果たした。デビュー当時から、目くるめくポップセンスを全開にした音楽性で音楽ファンの度肝を抜き、「マニアックなのにめちゃくちゃポップ」という独自の立ち位置を確立。プロデューサーを務めた冨田恵一(冨田ラボ)とともに、渋谷系ムーヴメント以降の新たな才能と称賛され、90年代末の音楽シーンに大きな楔を打った。2000年に発表した「エイリアンズ」は、当時こそ大きなヒットとはならなかったが、長い年月を経て名曲としての評価を高めたことからも、彼らの存在は非常に重要だったことがわかるだろう。
しかし、2013年に堀込泰行は脱退し、キリンジは堀込高樹を中心としたKIRINJIとして再スタート。バンド形態からソロ・ユニットへと変遷と進化をし続けているが、現在も変わらず圧倒的なポップ・ワールドを生み出し続けている。一方の堀込泰行は、キリンジ在籍時からソロ活動も並行して行い、当初は「馬の骨」という名義を使用していた。キリンジ脱退後もコンスタントに作品を発表し、同時に数多くの客演でも活躍している。また、ソングライターとしても非凡の才能を駆使し、YUKI、ハナレグミ、坂本真綾などへの楽曲提供も精力的に行っている。
トベタ・バジュンの「空想絵画」は、堀込泰行がまだキリンジ在籍時の2005年にレコーディングされている。かねてよりキリンジに魅了されていたということもあり、オファーを受けてもらえるかわからないまま、彼のヴォーカルを想定した歌詞とメロディを作り上げたという。そして縁あって、念願の共演が実現したのがこの曲というわけだ。当時のキリンジはいわば成熟期であり、個々のソロ活動がスタートしたタイミングでもあった。そういった意味でも、お互いの「何か新しいことをしたい」という意志がマッチングしたのかもしれない。
キリンジや堀込泰行のソロ(馬の骨)は、いわゆるバンド・サウンドがメインだったが、トベタ・バジュンは敢えてエレクトリックなトラックを用意したところがこの曲のポイントだ。80年代の坂本龍一を思わせるシンセサイザーをメインにしたビートとサウンドは、感情を込め過ぎないドライな感覚のヴォーカルと見事にフィットしている。まさに、堀込泰行のヴォーカリストとしての新たな一面をあぶり出したナンバーと言ってもいいだろう。タイトル通り、夢の中を彷徨っているような少々エロティックな歌詞とのバランスも美しい。
この2人のコラボレーションは、この一曲では終わらなかった。バンダイナムコの人気ゲーム『塊魂』のためにトベタ・バジュンがカタマリロボ名義で作った楽曲「ヒューストン」を、2009年にキリンジがリアレンジし、「ヒューストン (Re-Arranged by KIRINJI)」としてアルバム『「塊魂TRIBUTE」オリジナル・サウンドトラック「かたまりたけし」』に提供。これもまたドリーミーな極上ポップに仕上がっている。
さらに、2011年にはトベタ・バジュンはMACHO ROBOT(マッチョ・ロボット)名義で「Seaside Heaven 3000」という楽曲を発表し、堀込泰行のヴォーカルをフィーチャーした。この曲では「空想絵画」を軽く凌駕するファンキーなエレクトロ・サウンドを構築しており、あの歌声がダンス・ミュージックにも対応することができることを証明した。なお、この曲は後に「海辺の楽園」とタイトルもサウンドも一新し、杉山清貴のヴォーカルをフィーチャーした作品へと生まれ変わっている。
このように、「この人に歌って欲しい」という熱い想いから生まれた「空想絵画」は、その想いが一点にとどまることなく有機的に広がっていくということを物語る作品となった。まさに人と人とのつながりを大切にするトベタ・バジュンの音楽世界を象徴するかのような楽曲なのである。